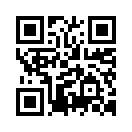2009年09月27日
これぞ、ベットナーム
こんばんは。
ここホーチミンも心なしか涼しくなってきたような気がします。
いや、心なしか。
気がするだけだと思います。
気温は30℃いってます。
うん、夏だ。
昨日は久しぶりに「ベトナム人」を肌で感じました。
ちょっとイラッとしちゃった日記です。
昨日のサッカースクール。
時刻はPM2:00。
送迎用のバスを待ちます。
来ません。
まぁよくあることなんです。
この辺はもう気にしません。
とりあえずバス会社に電話掛けます。
「ドライバーに確認するからちょっと待ってて。」
「はい。」
まぁね、5分とか10分とかならね。
10分経ちます。
バス来ません。
そんな気配微塵もありません。
通りすがりのセダンに「今日はこれか?」なんて言ってみます。
しかし、内心焦り始めます。
(子どものピックアップに一時間はかかるー!)
再び電話します。
“I don't care.”
「気にしない(?)」
意味がわかりません。
応答する間もなく電話切られます。
その後、掛けなおすも不通。
・・・・
PM2:25
ついに!
悠々と、そして堂々と登場。
もはやあっぱれ。
貫禄あります。
半ギレで乗り込む俺らを横目に
「知ってるベトナム語しゃべってみろよ」
は?
第一声それ?
謝罪は?
てかいきなりその会話?(苦笑)
初めて見るドライバー。
こういった質問に対して僕たち、普段なら喜んで答えます。
普段ならね。
おぼつかないベトナム語ですが、そんなコミュニケーションが楽しかったり。
普段ならね。
なぜ今日の遅刻野郎に限ってこんな気さくなおっちゃんなんだー!!
でも、優しいまっつは答えてやりましたよ。
知ってる単語、総動員して。
ちょっとだけ皮肉をこめて。
「なんで今日遅れたの?」
そしたら、おっさん
「渋滞してたんだよ。バイクがいっぱいでね。」
・・・・
うそだー
そんな混んでないよ?
いつもとあんま道変わんないよ?
てか自分の横見てよ!
あんた、まだ買って間もないであろう、氷がいっぱい入ったカップ横にあるよ?
絶対どっかのカフェでのんびりしてただろーがー。
よくそんな平然と答えられるね。
悪ぶれるそぶりもなしに。
それからも半ギレ状態の俺らに上から目線でベトナム語を要求する彼。
にゃいん、にゃいん(ベト語)
=「いそげーーー!!」
しかし、法の規律が薄いベトナムにおいて、
こやつはなぜか法廷速度厳守。
“Rimited speed.”
片言の英語はいらん。
それでも、こっちに来てちょっぴり大人になったまっつは作り笑顔で懸命に答える。
そしたら、なにやら話し出した・・・
You walk with me...
ん?
一緒に歩く??
違う、違う。
ベトナム人の英語は聞き取りにくい。。
You work with me.
なに?
一緒に働きたいの?
どうやら俺らの専属ドライバーになりたいような雰囲気。。。
おぇーーー!!!
自分あんなに遅刻したよ?
てかあなた仕事委託されてるんだよね?
仕事横取り?
それやっちゃう?
ねーやっちゃうの??
俺も河崎ももはや苦笑い。
そして、ついに彼は過ちを犯した。
何車線もある道路で別の車線に入りました。
そこは中央分離帯がある道路で車線のミスは致命的。
まぁ間違えちゃったんだね、君は。
そーいうこともあるよ。
急いでるけど。
そしたらね、、、
(本当はもうちょっといざこざがあったけど、)
うっすら笑って
“You are wrong...”
ええーーーー
おい!
今なんて言った?
間違えたの完全お前だろ。
俺のせい?
それ冗談?
全然笑えないよ?
「いい加減にせー!!こらーーー」
怒りのあまり横で地団太を踏み出す河崎。
あきれて物も言えない俺。
そんなこと冗談でも言えないよ。
この空気で。
“KY”ってこういうことか。
無論、仕事の話は交渉決裂。
てか、無視!!!
帰りのバス車内、バス仲介会社にメール送ってやりました。
“Today’s driver is too bad!!”
ぴろりん。
おっ返ってきた、返ってきた。
なになに・・・
Next time will be driver better.
うーーーん。。。
そうね、あなたも楽観的なのね。
言う相手を間違えました。
お国柄をなめてました。
そう、ここは、自由の国ベトナム。
ここホーチミンも心なしか涼しくなってきたような気がします。
いや、心なしか。
気がするだけだと思います。
気温は30℃いってます。
うん、夏だ。
昨日は久しぶりに「ベトナム人」を肌で感じました。
ちょっとイラッとしちゃった日記です。
昨日のサッカースクール。
時刻はPM2:00。
送迎用のバスを待ちます。
来ません。
まぁよくあることなんです。
この辺はもう気にしません。
とりあえずバス会社に電話掛けます。
「ドライバーに確認するからちょっと待ってて。」
「はい。」
まぁね、5分とか10分とかならね。
10分経ちます。
バス来ません。
そんな気配微塵もありません。
通りすがりのセダンに「今日はこれか?」なんて言ってみます。
しかし、内心焦り始めます。
(子どものピックアップに一時間はかかるー!)
再び電話します。
“I don't care.”
「気にしない(?)」
意味がわかりません。
応答する間もなく電話切られます。
その後、掛けなおすも不通。
・・・・
PM2:25
ついに!
悠々と、そして堂々と登場。
もはやあっぱれ。
貫禄あります。
半ギレで乗り込む俺らを横目に
「知ってるベトナム語しゃべってみろよ」
は?
第一声それ?
謝罪は?
てかいきなりその会話?(苦笑)
初めて見るドライバー。
こういった質問に対して僕たち、普段なら喜んで答えます。
普段ならね。
おぼつかないベトナム語ですが、そんなコミュニケーションが楽しかったり。
普段ならね。
なぜ今日の遅刻野郎に限ってこんな気さくなおっちゃんなんだー!!
でも、優しいまっつは答えてやりましたよ。
知ってる単語、総動員して。
ちょっとだけ皮肉をこめて。
「なんで今日遅れたの?」
そしたら、おっさん
「渋滞してたんだよ。バイクがいっぱいでね。」
・・・・
うそだー
そんな混んでないよ?
いつもとあんま道変わんないよ?
てか自分の横見てよ!
あんた、まだ買って間もないであろう、氷がいっぱい入ったカップ横にあるよ?
絶対どっかのカフェでのんびりしてただろーがー。
よくそんな平然と答えられるね。
悪ぶれるそぶりもなしに。
それからも半ギレ状態の俺らに上から目線でベトナム語を要求する彼。
にゃいん、にゃいん(ベト語)
=「いそげーーー!!」
しかし、法の規律が薄いベトナムにおいて、
こやつはなぜか法廷速度厳守。
“Rimited speed.”
片言の英語はいらん。
それでも、こっちに来てちょっぴり大人になったまっつは作り笑顔で懸命に答える。
そしたら、なにやら話し出した・・・
You walk with me...
ん?
一緒に歩く??
違う、違う。
ベトナム人の英語は聞き取りにくい。。
You work with me.
なに?
一緒に働きたいの?
どうやら俺らの専属ドライバーになりたいような雰囲気。。。
おぇーーー!!!
自分あんなに遅刻したよ?
てかあなた仕事委託されてるんだよね?
仕事横取り?
それやっちゃう?
ねーやっちゃうの??
俺も河崎ももはや苦笑い。
そして、ついに彼は過ちを犯した。
何車線もある道路で別の車線に入りました。
そこは中央分離帯がある道路で車線のミスは致命的。
まぁ間違えちゃったんだね、君は。
そーいうこともあるよ。
急いでるけど。
そしたらね、、、
(本当はもうちょっといざこざがあったけど、)
うっすら笑って
“You are wrong...”
ええーーーー
おい!
今なんて言った?
間違えたの完全お前だろ。
俺のせい?
それ冗談?
全然笑えないよ?
「いい加減にせー!!こらーーー」
怒りのあまり横で地団太を踏み出す河崎。
あきれて物も言えない俺。
そんなこと冗談でも言えないよ。
この空気で。
“KY”ってこういうことか。
無論、仕事の話は交渉決裂。
てか、無視!!!
帰りのバス車内、バス仲介会社にメール送ってやりました。
“Today’s driver is too bad!!”
ぴろりん。
おっ返ってきた、返ってきた。
なになに・・・
Next time will be driver better.
うーーーん。。。
そうね、あなたも楽観的なのね。
言う相手を間違えました。
お国柄をなめてました。
そう、ここは、自由の国ベトナム。
2009年09月23日
ビナBOO
ベトナム情報ガイド『VINABOO』に載っていたブックレビューを紹介します。

ちなみにこのVINABOOというのは日本語で書かれたフリーペーパーです。
在越の日本人なら『Sketch』と並んで一度は目を通したことがあるはず。
ローカル(いや、ある意味グローバル?笑)な話題ですみません。
昨日のトピックと重なる部分が大きくて、なおかつ共感できることも多かったので紹介します。
『貧困の僻地』 曽野綾子著 新潮社
貧困と格差。
現在日本で騒がれているそれらは、本当に「貧困」や「格差」と言えるのか。
有名作家の著者はカトリック教徒としても知られ、
長年「海外邦人宣教者活動援助後援会(通称JOMAS)」の代表を務めている。
JOMASは海外で働く日本人神父や修道女の活動に対して資金をつけるNGO団体である。
途上国へ援助する時、多くの組織には必ず善人めかした泥棒がいて貴重な寄付金が漏れるので、
JOMASの活動以外には資金を渡さず、援助した事業の完成を確認するため、
著者はほとんどの現場に足を運んでいる。
本著は主にそこでの体験をもとにしたエッセイ集である。
僻地では物資も食料も不足し、まともな医療を受けることは困難で、
その地に住む人々の夢は腹一杯に食べることである。
僻地とはどんな場所であるか、そしてそこでの貧困の実態がどんなものであるかを
筆者は伝えている。
翻って電気、水道、通信、テレビの電波、舗装道路、宅配便や通販のサービスも遍く行き届き、
自動車も電気製品も全国同じような値段で買える日本には僻地と呼べるものは無い。
国民は社会を機能させるために必要な教育も受けている。
急病になっても無料の救急車で運ばれて必要な医療が受けられる。
食べるものもある。
途上国の現実と比べると、本当の格差・貧困とはいえないというのが著者の意見である。
アフリカ諸国の他にもインドやカンボジアなどでのJOMASの医療・教育などの活動を
確かめに行った著者の豊富な体験が綴られている。
70代で松葉杖を突きながら現地に出かける著者の覚悟と、
キッパリとした態度に心を打たれる。
「世間はいい子ばかりでもなければ、人はみな平等ではない。」
それを認識した上で何をなすべきかが大切である
と説く著者の揺るぎない姿勢に勇気づけられる思いだ。
(※VINABOOより転載 長月氏)
「人はみな平等ではない。」という言葉が胸に刺さりませんか?
僕もこちらで生活するようになって、このことを強く意識するようになりました。
日本で暮らしていたときには考えたこともありませんでした。
「人類みな平等」が当たり前だと思っていました。
でも、眼前に広がる光景は、その言葉とは程遠い現実だったのです。
そして、この現実に絶望してしまうのではなく、
この事実を認識した上で、何をなすべきかが大切だという筆者の主張に心から共感します。
貧困の僻地で、彼らは「腹一杯に食べること」を夢に見ています。
かといって物資や食料を支援するだけでは根本的な解決にはならないし、
本当に必要なことは何かを考えた上での支援でなければ無になってしまいます。
おそらく課題は山積みでしょう。
この現実に対して、僕は無関心ではいられません。
比較するのは違うと思いますが、日本に住む私たちはどれだけ可能性に溢れていることでしょう。
子どもの将来がどれだけ無限に広がっていることでしょうか。
そんな子どもたちに、僕は大きな夢を見させてあげたい。
でも、
自分の夢をかなえるだけでいいのでしょうか?
自分ひとりが満たされればそれでいいのでしょうか?
直接的な支援をしてくださいということではありません。
まずは気に掛けるだけでいいんです。
関心を持つだけでいいんです。
たぶん前にも載せましたが、僕の好きな言葉と動画を改めて。
http://www.youtube.com/watch?v=1aWkKw_fO6k
「“愛”の反対は“憎しみ”ではなく“無関心”だ」 byマザー・テレサ
日本の本ってこっちだとなかなか手に入らないんです。
この本読みたいんですけど、今すぐには読めないし、
興味を持ってくれた人がいたらぜひ読んでみてください。
そして、感想教えてください。
そんでもって、ベトナムまで送ってくれちゃったりしたら嬉しいです♪笑
では、サッカー教えに行ってきまーす!
ちなみにこのVINABOOというのは日本語で書かれたフリーペーパーです。
在越の日本人なら『Sketch』と並んで一度は目を通したことがあるはず。
ローカル(いや、ある意味グローバル?笑)な話題ですみません。
昨日のトピックと重なる部分が大きくて、なおかつ共感できることも多かったので紹介します。
『貧困の僻地』 曽野綾子著 新潮社
貧困と格差。
現在日本で騒がれているそれらは、本当に「貧困」や「格差」と言えるのか。
有名作家の著者はカトリック教徒としても知られ、
長年「海外邦人宣教者活動援助後援会(通称JOMAS)」の代表を務めている。
JOMASは海外で働く日本人神父や修道女の活動に対して資金をつけるNGO団体である。
途上国へ援助する時、多くの組織には必ず善人めかした泥棒がいて貴重な寄付金が漏れるので、
JOMASの活動以外には資金を渡さず、援助した事業の完成を確認するため、
著者はほとんどの現場に足を運んでいる。
本著は主にそこでの体験をもとにしたエッセイ集である。
僻地では物資も食料も不足し、まともな医療を受けることは困難で、
その地に住む人々の夢は腹一杯に食べることである。
僻地とはどんな場所であるか、そしてそこでの貧困の実態がどんなものであるかを
筆者は伝えている。
翻って電気、水道、通信、テレビの電波、舗装道路、宅配便や通販のサービスも遍く行き届き、
自動車も電気製品も全国同じような値段で買える日本には僻地と呼べるものは無い。
国民は社会を機能させるために必要な教育も受けている。
急病になっても無料の救急車で運ばれて必要な医療が受けられる。
食べるものもある。
途上国の現実と比べると、本当の格差・貧困とはいえないというのが著者の意見である。
アフリカ諸国の他にもインドやカンボジアなどでのJOMASの医療・教育などの活動を
確かめに行った著者の豊富な体験が綴られている。
70代で松葉杖を突きながら現地に出かける著者の覚悟と、
キッパリとした態度に心を打たれる。
「世間はいい子ばかりでもなければ、人はみな平等ではない。」
それを認識した上で何をなすべきかが大切である
と説く著者の揺るぎない姿勢に勇気づけられる思いだ。
(※VINABOOより転載 長月氏)
「人はみな平等ではない。」という言葉が胸に刺さりませんか?
僕もこちらで生活するようになって、このことを強く意識するようになりました。
日本で暮らしていたときには考えたこともありませんでした。
「人類みな平等」が当たり前だと思っていました。
でも、眼前に広がる光景は、その言葉とは程遠い現実だったのです。
そして、この現実に絶望してしまうのではなく、
この事実を認識した上で、何をなすべきかが大切だという筆者の主張に心から共感します。
貧困の僻地で、彼らは「腹一杯に食べること」を夢に見ています。
かといって物資や食料を支援するだけでは根本的な解決にはならないし、
本当に必要なことは何かを考えた上での支援でなければ無になってしまいます。
おそらく課題は山積みでしょう。
この現実に対して、僕は無関心ではいられません。
比較するのは違うと思いますが、日本に住む私たちはどれだけ可能性に溢れていることでしょう。
子どもの将来がどれだけ無限に広がっていることでしょうか。
そんな子どもたちに、僕は大きな夢を見させてあげたい。
でも、
自分の夢をかなえるだけでいいのでしょうか?
自分ひとりが満たされればそれでいいのでしょうか?
直接的な支援をしてくださいということではありません。
まずは気に掛けるだけでいいんです。
関心を持つだけでいいんです。
たぶん前にも載せましたが、僕の好きな言葉と動画を改めて。
http://www.youtube.com/watch?v=1aWkKw_fO6k
「“愛”の反対は“憎しみ”ではなく“無関心”だ」 byマザー・テレサ
日本の本ってこっちだとなかなか手に入らないんです。
この本読みたいんですけど、今すぐには読めないし、
興味を持ってくれた人がいたらぜひ読んでみてください。
そして、感想教えてください。
そんでもって、ベトナムまで送ってくれちゃったりしたら嬉しいです♪笑
では、サッカー教えに行ってきまーす!
2009年09月22日
アンフェア
今日のYahoo!ニュースにこんな記事が載っていました。
みなさんはどのように考えますか?
読売新聞社が英BBC放送と共同実施した20か国対象の世論調査で、自国で経済的な豊かさが公平に行き渡っているかどうかを聞いたところ、日本では「公平だ」と思う人は16%にとどまり、「公平ではない」が72%に達した。

「公平ではない」はフランスの84%が最高で、日本はロシア、トルコ各77%、ドイツ76%、フィリピン74%に続いて高く、国民が「格差」を強く感じていることを浮き彫りにした。
「公平ではない」という答えは日本を含む17か国で多数を占めた。米国は「公平だ41%―公平ではない55%」、英国は「公平だ39%―公平ではない57%」、中国は「公平だ44%―公平ではない49%」となった。「公平だ」と思う人が最も多かったのはオーストラリアで64%に上った。カナダは過半数の58%で、インドは「公平だ」44%、「公平ではない」27%だった。
政府が景気対策のため財政支出を大幅に増やすことへの賛否を聞くと、日本では賛成47%、反対36%だった。15か国で賛成が反対を上回り、政府が果たす役割への期待は高かった。
調査は6月から8月にかけて、面接または電話で実施し、読売新聞社は日本国内分を担当した。
(※Yahoo!ニュースより転載)
「公平」ってなんでしょう?
「格差」ってなんでしょう?
「幸せ」ってなんでしょう?
とてつもなく大きな問いなので未熟な若造が意見を述べるのも気が引けるのですが、一応私見を。
この調査が具体的にどんな人々を対象にしているかはわかりませんが、
(階級や階層によって、その捉え方は大きく異なると思います。)
日本人の「公平or不公平」の水準ってものすごく高いところにあると思います。
少なくとも僕の見てきたベトナムとかカンボジアなど発展途上と言われる国々と比較すれば。
こうした国々では、そもそも何が「公平」なのか、それ自体を判断する基準を“知らない”という
問題が往々にしてあると思います。
近年、この調査にもあるように日本でも「格差社会」という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。
しかし、真の「格差」ってなんでしょう。
あくまで人に聞いたり、僕が感じたことなので、すべてではありませんが、
日本ほど経済的に格差の小さい国はないのではないでしょうか。
今生活している東南アジア諸国や“お隣”韓国、アメリカ、アフリカなど、
世界では日本と比べられないほど格差が大きいといいます。
具体的に言うと、日本では格差といえど社会全体で見れば中間層が大多数を占め、
他方、先述の国々では中間層が非常に少なく、富裕層か貧困層か、その両極端だと。
こちらの生活の中でも感じることがあるのですが、経済システムとしても、
外資や、外国人などがその国に落としていく大きなお金は、大概、富裕層の懐に入っていきます。
その恩恵を受けることは、貧困層では、道路をはじめとするインフラなど、その結果でしかない。
よって、どんなに経済が成長してもその格差は両端に広がっていく一方なのです。
日本にも億万長者とか富裕層とか、それに値する人はいると思うんですが、
比較される人々も多くはある程度の生活水準が保たれていると思うんです。
だから、日本人が「公平だ、不公平だ」というときの水準ってすごく高いんじゃないかと思います。
そもそも、階級とか階層とかって意識したことありますか?
恥ずかしながら、僕は大学の研究でその話が出るまで意識したことはありませんでした。
人間の“欲求”の話で、
あるものを買ってあげたら、今度はもっといいものを、
それが手に入ったら今度はもっともっといいものを、、
とより高次のものを手に入れたがるのが欲求の性質だと勉強したような気がするのですが、
物質的に多くを満たされた日本という国において、
そこに生きる人々が次に求めるものって「当たり前」のものじゃ満たされないんじゃないでしょうか。
その「当たり前」・・・
発展途上国といわれる国々で、それは当たり前でしょうか?
日常的に享受されているものでしょうか?
この辺の問題、すごく難しいですねー
頭が痛くなりますねー
そもそも“資本主義”っていう、現在世界経済の大筋となっている考え方は
格差を生み出すことを前提として作られた経済システムですから、
すべての国の人々を平等に豊かにしようとすることは不可能だし、
そんなことしたら世界経済が崩壊しちゃいます。
でも、世界の貧困の現実を目の当たりにすると、このままでいいのかな?
何かできることはないのかな?って思っちゃいます。
もちろん、それぞれの生活にはそれぞれの「幸せ」があって、
経済的に優れた国の人が貧しい人々を・・・と考えること自体、
経済的強者の発想なのかもしれません。
僕が見てきた中にも、
一見「貧しいな(※経済的に)」と思われる人も生活は笑顔に満たされて実に幸せそうで、
経済的に豊かな日本で暮らす人々よりも幸せなんじゃないかと思ったり、
「幸せ」って何なんだ?って思ってみたり、
貧国に暮らす人々の力強い生き方が私たちに教えてくれることって本当に大きいと思います。
しかし、いまだに戦争を繰り返す国や地域があったり、
日々不発弾や地雷など戦争の「負の遺産」の恐怖と隣り合わせに生活している人々がいたり、
こうした現実を見ると、何とかしたい!何とかしなければ!って思います。
ある子どもが言いました。
「戦争はもう終わったけど・・・」
終わってません。
戦争は今なお世界各地で起きています。
「負の遺産」と日々戦っている人がいます。
戦争によって与えられた精神的ダメージと戦っている人がいます。
悲しみ・苦しみ・憎しみと戦い続けている人がいます。
戦争は過去の話ではありません。
戦争という直接的な形にせよ、間接的にせよ、現在進行中なのです。
あー出た。
まっつ(←最近いただいたあだ名です。)の悪い癖です。
話が止めどなく広がっていきます。
すみません、長々と。。
要は何を言いたいかと言うと、
①「幸せ」はその人の心が決める。(mixiのコミュニティにこんなんあったような?)
②しかし、厳然たる世界の現実を前にして私たちができることは何なのか。
③そして、その第一歩となるのは、まず「知る」こと、「認める」こと。
このブログを通して、日本に暮らす人たちが世界を「知る」手助けができれば、と思うわけです。
今はまだ、そんなデカい事はできませんが、身近な人から発信していこうと思うわけです。
微力でもいいんです。
まだ自分の器が追いついていないので。
とまぁ、篠原涼子のように「アンフェア」に立ち向かっていくことを決心した、
まっつ(←けっこう気に入ってます。笑)でした。
では。
最後まで根気強く読んでくれた方、
ありがとうございました。
みなさんはどのように考えますか?
読売新聞社が英BBC放送と共同実施した20か国対象の世論調査で、自国で経済的な豊かさが公平に行き渡っているかどうかを聞いたところ、日本では「公平だ」と思う人は16%にとどまり、「公平ではない」が72%に達した。

「公平ではない」はフランスの84%が最高で、日本はロシア、トルコ各77%、ドイツ76%、フィリピン74%に続いて高く、国民が「格差」を強く感じていることを浮き彫りにした。
「公平ではない」という答えは日本を含む17か国で多数を占めた。米国は「公平だ41%―公平ではない55%」、英国は「公平だ39%―公平ではない57%」、中国は「公平だ44%―公平ではない49%」となった。「公平だ」と思う人が最も多かったのはオーストラリアで64%に上った。カナダは過半数の58%で、インドは「公平だ」44%、「公平ではない」27%だった。
政府が景気対策のため財政支出を大幅に増やすことへの賛否を聞くと、日本では賛成47%、反対36%だった。15か国で賛成が反対を上回り、政府が果たす役割への期待は高かった。
調査は6月から8月にかけて、面接または電話で実施し、読売新聞社は日本国内分を担当した。
(※Yahoo!ニュースより転載)
「公平」ってなんでしょう?
「格差」ってなんでしょう?
「幸せ」ってなんでしょう?
とてつもなく大きな問いなので未熟な若造が意見を述べるのも気が引けるのですが、一応私見を。
この調査が具体的にどんな人々を対象にしているかはわかりませんが、
(階級や階層によって、その捉え方は大きく異なると思います。)
日本人の「公平or不公平」の水準ってものすごく高いところにあると思います。
少なくとも僕の見てきたベトナムとかカンボジアなど発展途上と言われる国々と比較すれば。
こうした国々では、そもそも何が「公平」なのか、それ自体を判断する基準を“知らない”という
問題が往々にしてあると思います。
近年、この調査にもあるように日本でも「格差社会」という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。
しかし、真の「格差」ってなんでしょう。
あくまで人に聞いたり、僕が感じたことなので、すべてではありませんが、
日本ほど経済的に格差の小さい国はないのではないでしょうか。
今生活している東南アジア諸国や“お隣”韓国、アメリカ、アフリカなど、
世界では日本と比べられないほど格差が大きいといいます。
具体的に言うと、日本では格差といえど社会全体で見れば中間層が大多数を占め、
他方、先述の国々では中間層が非常に少なく、富裕層か貧困層か、その両極端だと。
こちらの生活の中でも感じることがあるのですが、経済システムとしても、
外資や、外国人などがその国に落としていく大きなお金は、大概、富裕層の懐に入っていきます。
その恩恵を受けることは、貧困層では、道路をはじめとするインフラなど、その結果でしかない。
よって、どんなに経済が成長してもその格差は両端に広がっていく一方なのです。
日本にも億万長者とか富裕層とか、それに値する人はいると思うんですが、
比較される人々も多くはある程度の生活水準が保たれていると思うんです。
だから、日本人が「公平だ、不公平だ」というときの水準ってすごく高いんじゃないかと思います。
そもそも、階級とか階層とかって意識したことありますか?
恥ずかしながら、僕は大学の研究でその話が出るまで意識したことはありませんでした。
人間の“欲求”の話で、
あるものを買ってあげたら、今度はもっといいものを、
それが手に入ったら今度はもっともっといいものを、、
とより高次のものを手に入れたがるのが欲求の性質だと勉強したような気がするのですが、
物質的に多くを満たされた日本という国において、
そこに生きる人々が次に求めるものって「当たり前」のものじゃ満たされないんじゃないでしょうか。
その「当たり前」・・・
発展途上国といわれる国々で、それは当たり前でしょうか?
日常的に享受されているものでしょうか?
この辺の問題、すごく難しいですねー
頭が痛くなりますねー
そもそも“資本主義”っていう、現在世界経済の大筋となっている考え方は
格差を生み出すことを前提として作られた経済システムですから、
すべての国の人々を平等に豊かにしようとすることは不可能だし、
そんなことしたら世界経済が崩壊しちゃいます。
でも、世界の貧困の現実を目の当たりにすると、このままでいいのかな?
何かできることはないのかな?って思っちゃいます。
もちろん、それぞれの生活にはそれぞれの「幸せ」があって、
経済的に優れた国の人が貧しい人々を・・・と考えること自体、
経済的強者の発想なのかもしれません。
僕が見てきた中にも、
一見「貧しいな(※経済的に)」と思われる人も生活は笑顔に満たされて実に幸せそうで、
経済的に豊かな日本で暮らす人々よりも幸せなんじゃないかと思ったり、
「幸せ」って何なんだ?って思ってみたり、
貧国に暮らす人々の力強い生き方が私たちに教えてくれることって本当に大きいと思います。
しかし、いまだに戦争を繰り返す国や地域があったり、
日々不発弾や地雷など戦争の「負の遺産」の恐怖と隣り合わせに生活している人々がいたり、
こうした現実を見ると、何とかしたい!何とかしなければ!って思います。
ある子どもが言いました。
「戦争はもう終わったけど・・・」
終わってません。
戦争は今なお世界各地で起きています。
「負の遺産」と日々戦っている人がいます。
戦争によって与えられた精神的ダメージと戦っている人がいます。
悲しみ・苦しみ・憎しみと戦い続けている人がいます。
戦争は過去の話ではありません。
戦争という直接的な形にせよ、間接的にせよ、現在進行中なのです。
あー出た。
まっつ(←最近いただいたあだ名です。)の悪い癖です。
話が止めどなく広がっていきます。
すみません、長々と。。
要は何を言いたいかと言うと、
①「幸せ」はその人の心が決める。(mixiのコミュニティにこんなんあったような?)
②しかし、厳然たる世界の現実を前にして私たちができることは何なのか。
③そして、その第一歩となるのは、まず「知る」こと、「認める」こと。
このブログを通して、日本に暮らす人たちが世界を「知る」手助けができれば、と思うわけです。
今はまだ、そんなデカい事はできませんが、身近な人から発信していこうと思うわけです。
微力でもいいんです。
まだ自分の器が追いついていないので。
とまぁ、篠原涼子のように「アンフェア」に立ち向かっていくことを決心した、
まっつ(←けっこう気に入ってます。笑)でした。
では。
最後まで根気強く読んでくれた方、
ありがとうございました。
2009年09月14日
金子せんせい
今日のベトナムはパッとしない天気です。
まるで愚図ついた赤ちゃんのようでした。
そこで一節。
朝 晴れたと思うたら
昼前 雨がパーラパラ
昼 晴れたと思うたら
昼過ぎ 雨がザーバザバ
サッカー行くまえ 雨降ったと思うたが
着いたら 雨上がり 決死隊。
なんじゃこりゃ。
あー「詩」って難しい。
センスねー。笑
そんな詩の天才「金子みすず」さんの詩をいくつかご紹介します。
~わたしと小鳥と鈴と~
わたしが両手を広げても
お空はちっとも飛べないが
飛べる小鳥は私のように
地べたを速くは走れない
私が体をゆすっても
きれいな音は出ないけど
あの鳴る鈴は私のように
たくさんな唄は知らないよ
鈴と小鳥と それから私
みんな違って みんないい
これですよ、僕が言いたかったのは。
詩で表現できちゃう金子せんせいのセンスに脱帽。
続いて、こちら。
~星とタンポポ~
青いお空のそこ深く
海の小石のそのように
夜がくるまで沈んでる
昼のお星は眼に見えぬ
見えぬけれどもあるんだよ
見えぬものでもあるんだよ
散ってすがれたタンポポの
川原のすきにだぁまって
春のくるまでかくれてる
強いその根は眼に見えぬ
見えぬけれどもあるんだよ
見えぬものでもあるんだよ
人間って目に見えるものにすがりたがるけど、
見えないものでも確かにそこにあるんですよね。
もしかしたら目に見えないものの方が実は強いのかもしれません。
Rさんのコメントで金子みすずさんの詩に久しぶりに再会したんですけど、、、
めっちゃいい!!!
ものすごく共感。
そんでもって、リズムに乗ってすっーと入ってくる感じがたまらない。
こういう詩を書ける感性の持ち主に生まれたかったなー
ということで、変てこ詩人マツノの、変てこな詩による、変てこな日記でした。。
でもね、
グランド駆ける 彼らの笑顔は 今日も快晴。
まるで愚図ついた赤ちゃんのようでした。
そこで一節。
朝 晴れたと思うたら
昼前 雨がパーラパラ
昼 晴れたと思うたら
昼過ぎ 雨がザーバザバ
サッカー行くまえ 雨降ったと思うたが
着いたら 雨上がり 決死隊。
なんじゃこりゃ。
あー「詩」って難しい。
センスねー。笑
そんな詩の天才「金子みすず」さんの詩をいくつかご紹介します。
~わたしと小鳥と鈴と~
わたしが両手を広げても
お空はちっとも飛べないが
飛べる小鳥は私のように
地べたを速くは走れない
私が体をゆすっても
きれいな音は出ないけど
あの鳴る鈴は私のように
たくさんな唄は知らないよ
鈴と小鳥と それから私
みんな違って みんないい
これですよ、僕が言いたかったのは。
詩で表現できちゃう金子せんせいのセンスに脱帽。
続いて、こちら。
~星とタンポポ~
青いお空のそこ深く
海の小石のそのように
夜がくるまで沈んでる
昼のお星は眼に見えぬ
見えぬけれどもあるんだよ
見えぬものでもあるんだよ
散ってすがれたタンポポの
川原のすきにだぁまって
春のくるまでかくれてる
強いその根は眼に見えぬ
見えぬけれどもあるんだよ
見えぬものでもあるんだよ
人間って目に見えるものにすがりたがるけど、
見えないものでも確かにそこにあるんですよね。
もしかしたら目に見えないものの方が実は強いのかもしれません。
Rさんのコメントで金子みすずさんの詩に久しぶりに再会したんですけど、、、
めっちゃいい!!!
ものすごく共感。
そんでもって、リズムに乗ってすっーと入ってくる感じがたまらない。
こういう詩を書ける感性の持ち主に生まれたかったなー
ということで、変てこ詩人マツノの、変てこな詩による、変てこな日記でした。。
でもね、
グランド駆ける 彼らの笑顔は 今日も快晴。
2009年09月13日
せんせい、あのね。
こちら、豪雨ベトナムからお送りいたします。
日中は鉄板の上で焼かれるような強すぎる!日差しであったにも関わらず、
今は一転して豪雨。
スコールです。
そんな気まぐれな天気がベトナムを感じさせますね。
照りつける日の下で、大人がへばりそうになるのを尻目に子ども達は今日も元気!!
「髪の毛がフライパンのように熱くなっているよ~」
と、ケラケラ笑いながらボールを追いかけ回っています。
そうです、彼らは無敵なのです。
そんな子ども達を見て、コーチは、もう若くない体を奮い起こすのであります。
がんばれ、俺。
さて、先日の日記ですこーしだけ触れましたが、2学期から「先生」してます。
補習校という、インターナショナルスクールやベトナムの現地校に通う子ども達のために、
日本語で学習する場を与える日本的学力の補足的な学校です。
そこで、小学校一年生に「国語」を教えています。
要するに、またまた“我が子”が増えてしまったというわけです。
嬉しいこと、この上ありません。
小学校一年生と言えば、、、そうです。
「動物」とも「宇宙人」とも形容される非常に活発な子ども達です。
自分のエネルギーを自分の中に留めておけないみなぎるパワーの持ち主たちです。
うちの洗面所のパイプから滴り落ちる水漏れの比になりません。
もはや垂れ流しです。笑
そんな子ども達に、学生時代、松野の最も苦手としていた「国語」を教えることになるとは
思ってもみませんでした。
しかも、このベトナムの地でね。
みなさん、小学校一年生の頃に何を勉強していましたか?
とおーーい記憶を呼び起こしてみましょう。
ほらほら、何かが聞こえてくるよ。
みみを あてたら きこえたよ。(「おむすび ころりん」風に)
「うんとこしょ、どっこいしょ。」
それでも、かぶは ぬけません。
まごは 犬を よんできました。
かぶを おじいさんが ひっぱって、
おじいさんを おばあさんが ひっぱって、
おばあさんが まごを ひっぱって、
まごを 犬が ひっぱって、
「うんとこしょ、どっこいしょ。」
まだまだ かぶは ぬけません。
不朽の名作、「大きなかぶ」です。

自分のあの頃を思い出しました。
狭い教室で劇なんかしちゃったような気もします。
やさしい、やさしい、まつのせんせいは、
一人6役をこなしながらみんなに読み聞かせてあげるわけです。
「とうとう、かぶは ぬけました。」の後には、もう、拍手喝采ですよ。笑
読み聞かせをしながら気づいたことは、日本語の生み出すリズムってすごく美しい。
ってこと。
特に、小学校一年生の「国語」の教科書って、
リズムとか流れるような語調を重視して作られてるから、
その文章が織り成す世界が美しいこと。
数年前に『声に出して読みたい 日本語』がベストセラーになりましたが、
お子さんのいるご家庭や、奇跡的にうちに教科書が残っている!!という人は、
ぜひ小学生の教科書を音読してみてください。
その日本語的な美しさに引き込まれること、間違いなし!
生徒たちには音読カードを作って、宿題として音読を家庭学習させていますが、
宿題を手伝う、お母様方!!
めんどくさいと思わずに自分が楽しむつもりで付き合ってあげてください。
案外、自分がハマっちゃうかもしれませんよ。笑
もう一つは、子どもの無限の想像力。
よく子どもは、何度も何度も、同じ絵本を「よんで~」と迫ってきますよね。
僕たち大人が読んでも、一つの文章から描かれる世界は一つかもしれないけど、
彼らにとっては、一回、一回、頭に思い浮かべられる世界は違うのだと思います。
いわば、一人ひとりの「ワールド」です。
だから、飽きないんです。
これって子どもの才能ですよね。
特権ですよね。
私たちは、いつからそんなに想像力が乏しくなってしまったのでしょうか。。
歳をとるにつれて増えていくものと、失われていくもの。
知らず知らずに失われているものって実は、とても尊いものなのかもしれませんね。
読み聞かせをしながら、教卓から眺める彼ら一人ひとりの表情は、
まつのせんせいにとって至福のひと時でした。
そしてそして、もう一つ。
今日は長いですよー。
もう少しだけお付き合い願います。
気づいた人もいるかもしれませんが、「国語」にあえて括弧付けをしました。
なぜかというと、
この補習校の最大の特徴でもあると思うのですが、
中には「日本語」が「国語」でない子もいるのです。
あんまり極端に書くと“差別”とか言われてしまいそうなので慎重になってしまいますが、
僕はこのことをすごく素敵なことだと思っています。
両親とも日本人の子がいれば、一方は日本人で、
もう一方はベトナム人とか、アメリカ人とか、ヨーロッパ系の人とか本当に各家庭の状況は様々です。
そんな環境の中で、何が「国語」か?なんて問いは、愚問のような気がします。
もちろん、日本人向けの補習校なので形は「国語」になっていますが、
そんなの関係ねぇーってね。(あれ?死語ですか?笑)
こちらで生活するようになって思うことは国籍とか人種とかって、
そんなに関係ないんじゃないかなって思います。
もちろん、語弊がないように付け加えておきますが、
それぞれの文化の特徴とか気質とか素晴らしい部分はたくさんあるし、
それらを一緒くたにしてしまうことはとても危険なことです。
ですが、「人」と「人」とが付き合う上で、国が違うからとかって
特に意識する必要なんてないんじゃないでしょうか。
「外人」って表現、あまり好きではありません。
日本って島国ってこともあって「外」と「内」を無意識にも、
常に意識して生活してきた国だと思うんです。
そういう国に生まれて生きてきて、
無意識に自分の中にも見えない「壁」みたいなものを作っていたのかもって思うときがあります。
日本人って外国人と接するときすごい身構えますよね。
そういうことです。
物事には必ず例外が伴うので、ブログを書くときはいつも慎重になるのですが、
あくまで世間知らずの未熟者が一個人の意見として話すことなので多めに見てやってください。
日本人の中にもそういう人でないもたくさんいるし、
日本以外の人でもそうである人もたくさんいると思います。
なので、すべてを一概には言えませんが、
僕たちは「日本人」でありながら「世界人」なんですよね。
歴史の中で日本が「島国」であることって
結構、重要な意味を持ってたんじゃないかなって思ったりします。
すみません、ついつい長くなりました。
ブログ読んで気づいたことがあれば、どんどんコメントください。
批判でも、おちゃらけな意見でも、何でも。
一つ一つのコメントが励みになりますし、
自分の価値観をみがく研磨剤になってくれると確信しています。
ということで、
昨日生まれて初めて「韓国人」に見えると言われ、
〝VIETNAMESE AMERICAN〝の方に
〝JAPANESE KOREAN〝と命名された松野が
ベトナムよりお送りいたしました。
知らぬ間に雨も止んでいます。
では。
と、思ったらまた降り出しました。
日中は鉄板の上で焼かれるような強すぎる!日差しであったにも関わらず、
今は一転して豪雨。
スコールです。
そんな気まぐれな天気がベトナムを感じさせますね。
照りつける日の下で、大人がへばりそうになるのを尻目に子ども達は今日も元気!!
「髪の毛がフライパンのように熱くなっているよ~」
と、ケラケラ笑いながらボールを追いかけ回っています。
そうです、彼らは無敵なのです。
そんな子ども達を見て、コーチは、もう若くない体を奮い起こすのであります。
がんばれ、俺。
さて、先日の日記ですこーしだけ触れましたが、2学期から「先生」してます。
補習校という、インターナショナルスクールやベトナムの現地校に通う子ども達のために、
日本語で学習する場を与える日本的学力の補足的な学校です。
そこで、小学校一年生に「国語」を教えています。
要するに、またまた“我が子”が増えてしまったというわけです。
嬉しいこと、この上ありません。
小学校一年生と言えば、、、そうです。
「動物」とも「宇宙人」とも形容される非常に活発な子ども達です。
自分のエネルギーを自分の中に留めておけないみなぎるパワーの持ち主たちです。
うちの洗面所のパイプから滴り落ちる水漏れの比になりません。
もはや垂れ流しです。笑
そんな子ども達に、学生時代、松野の最も苦手としていた「国語」を教えることになるとは
思ってもみませんでした。
しかも、このベトナムの地でね。
みなさん、小学校一年生の頃に何を勉強していましたか?
とおーーい記憶を呼び起こしてみましょう。
ほらほら、何かが聞こえてくるよ。
みみを あてたら きこえたよ。(「おむすび ころりん」風に)
「うんとこしょ、どっこいしょ。」
それでも、かぶは ぬけません。
まごは 犬を よんできました。
かぶを おじいさんが ひっぱって、
おじいさんを おばあさんが ひっぱって、
おばあさんが まごを ひっぱって、
まごを 犬が ひっぱって、
「うんとこしょ、どっこいしょ。」
まだまだ かぶは ぬけません。
不朽の名作、「大きなかぶ」です。
自分のあの頃を思い出しました。
狭い教室で劇なんかしちゃったような気もします。
やさしい、やさしい、まつのせんせいは、
一人6役をこなしながらみんなに読み聞かせてあげるわけです。
「とうとう、かぶは ぬけました。」の後には、もう、拍手喝采ですよ。笑
読み聞かせをしながら気づいたことは、日本語の生み出すリズムってすごく美しい。
ってこと。
特に、小学校一年生の「国語」の教科書って、
リズムとか流れるような語調を重視して作られてるから、
その文章が織り成す世界が美しいこと。
数年前に『声に出して読みたい 日本語』がベストセラーになりましたが、
お子さんのいるご家庭や、奇跡的にうちに教科書が残っている!!という人は、
ぜひ小学生の教科書を音読してみてください。
その日本語的な美しさに引き込まれること、間違いなし!
生徒たちには音読カードを作って、宿題として音読を家庭学習させていますが、
宿題を手伝う、お母様方!!
めんどくさいと思わずに自分が楽しむつもりで付き合ってあげてください。
案外、自分がハマっちゃうかもしれませんよ。笑
もう一つは、子どもの無限の想像力。
よく子どもは、何度も何度も、同じ絵本を「よんで~」と迫ってきますよね。
僕たち大人が読んでも、一つの文章から描かれる世界は一つかもしれないけど、
彼らにとっては、一回、一回、頭に思い浮かべられる世界は違うのだと思います。
いわば、一人ひとりの「ワールド」です。
だから、飽きないんです。
これって子どもの才能ですよね。
特権ですよね。
私たちは、いつからそんなに想像力が乏しくなってしまったのでしょうか。。
歳をとるにつれて増えていくものと、失われていくもの。
知らず知らずに失われているものって実は、とても尊いものなのかもしれませんね。
読み聞かせをしながら、教卓から眺める彼ら一人ひとりの表情は、
まつのせんせいにとって至福のひと時でした。
そしてそして、もう一つ。
今日は長いですよー。
もう少しだけお付き合い願います。
気づいた人もいるかもしれませんが、「国語」にあえて括弧付けをしました。
なぜかというと、
この補習校の最大の特徴でもあると思うのですが、
中には「日本語」が「国語」でない子もいるのです。
あんまり極端に書くと“差別”とか言われてしまいそうなので慎重になってしまいますが、
僕はこのことをすごく素敵なことだと思っています。
両親とも日本人の子がいれば、一方は日本人で、
もう一方はベトナム人とか、アメリカ人とか、ヨーロッパ系の人とか本当に各家庭の状況は様々です。
そんな環境の中で、何が「国語」か?なんて問いは、愚問のような気がします。
もちろん、日本人向けの補習校なので形は「国語」になっていますが、
そんなの関係ねぇーってね。(あれ?死語ですか?笑)
こちらで生活するようになって思うことは国籍とか人種とかって、
そんなに関係ないんじゃないかなって思います。
もちろん、語弊がないように付け加えておきますが、
それぞれの文化の特徴とか気質とか素晴らしい部分はたくさんあるし、
それらを一緒くたにしてしまうことはとても危険なことです。
ですが、「人」と「人」とが付き合う上で、国が違うからとかって
特に意識する必要なんてないんじゃないでしょうか。
「外人」って表現、あまり好きではありません。
日本って島国ってこともあって「外」と「内」を無意識にも、
常に意識して生活してきた国だと思うんです。
そういう国に生まれて生きてきて、
無意識に自分の中にも見えない「壁」みたいなものを作っていたのかもって思うときがあります。
日本人って外国人と接するときすごい身構えますよね。
そういうことです。
物事には必ず例外が伴うので、ブログを書くときはいつも慎重になるのですが、
あくまで世間知らずの未熟者が一個人の意見として話すことなので多めに見てやってください。
日本人の中にもそういう人でないもたくさんいるし、
日本以外の人でもそうである人もたくさんいると思います。
なので、すべてを一概には言えませんが、
僕たちは「日本人」でありながら「世界人」なんですよね。
歴史の中で日本が「島国」であることって
結構、重要な意味を持ってたんじゃないかなって思ったりします。
すみません、ついつい長くなりました。
ブログ読んで気づいたことがあれば、どんどんコメントください。
批判でも、おちゃらけな意見でも、何でも。
一つ一つのコメントが励みになりますし、
自分の価値観をみがく研磨剤になってくれると確信しています。
ということで、
昨日生まれて初めて「韓国人」に見えると言われ、
〝VIETNAMESE AMERICAN〝の方に
〝JAPANESE KOREAN〝と命名された松野が
ベトナムよりお送りいたしました。
知らぬ間に雨も止んでいます。
では。
と、思ったらまた降り出しました。
2009年09月08日
拝啓 パソコン様
パソコン誘拐されました。
そして、今日帰ってきました。
おかえり。
会いたかったよ。
ということで、久々の日記更新です。
みなさん、いかがお過ごしでしたでしょうか?
日本はもうすっかり秋ですか?
運動会ですか?
ココロはすでにお祭り気分ですか?
お囃子の音が聞こえてきそうですね。
キンモクセイが香ってきそうですね。
掛川人はきっと血が騒ぎ出していることでしょう。
しかーし!
ベトナムは夏です。
相も変わらず夏です。
懲りずに夏です。
一年中夏です。
・・・秋よ、来い。
なんだかんだ2週間近くネットが不調で、ブログにはノータッチでした。
ネットに依存しているわけではありませんが、あると便利です。
いや、必須です。
海外では、日本の情報が入ってきません。
そんな愛しのパソコンが帰ってきました。
先週、ベトナム人の修理屋さんにお願いして、今日やっとこさ戻ってきました。
ウイルスだか何だかわかんないけど、帰ってきて何より。
データ失われてなくて何より。
壊されてなくて何より。。
ベトナムにしては結構高い値段とられてショックだけど、
パソコンに無知な俺にはしょうがない。
と、思いたいとこだけど・・・
たぶん原因はパソコンじゃなくて、アパートのインターネットケーブルにあったと思われる。
いや、絶対にケーブルだ!
修理のあんちゃんが修理したパソコン持ってきて繋いだら、
結局、修理前と接続状態あんまり変わらなくて、
あんちゃん困ったような顔してて、
微妙な沈黙つづいて、
挙句の果てに
「これはケーブルが悪いね。」
って言い出して、
大家さんにケーブル変えてもらったら、
つながった!!
って、、、
どういうこと!?
あんた「松野さんのパソコンはウイルスです・・・」
ってよくわからん片言の日本語で言うてたやん!!
ウイルスは???
いずこへ!?
まぁーそんなこんなもベトナムですな。
Take it easy!!
気楽にいきましょう。
さて、ネット世界から断絶されている間に、
日本では総選挙おわってました。
民主圧勝、自民大敗。
政治のことはよくわかりませんが、
日本よ、頼むから良くなってくれ!
国民は不安でなりません。
今はベトナム国民と化していますが。笑
日本に帰る頃までには政局が安定してるといいな。
ということで、海外においてパソコンがいかに重宝されるか、身に染みてわかった二週間でした。
敬具
追伸 小学校1年生の「国語の先生」始めました♪
まつのせんせいより
そして、今日帰ってきました。
おかえり。
会いたかったよ。
ということで、久々の日記更新です。
みなさん、いかがお過ごしでしたでしょうか?
日本はもうすっかり秋ですか?
運動会ですか?
ココロはすでにお祭り気分ですか?
お囃子の音が聞こえてきそうですね。
キンモクセイが香ってきそうですね。
掛川人はきっと血が騒ぎ出していることでしょう。
しかーし!
ベトナムは夏です。
相も変わらず夏です。
懲りずに夏です。
一年中夏です。
・・・秋よ、来い。
なんだかんだ2週間近くネットが不調で、ブログにはノータッチでした。
ネットに依存しているわけではありませんが、あると便利です。
いや、必須です。
海外では、日本の情報が入ってきません。
そんな愛しのパソコンが帰ってきました。
先週、ベトナム人の修理屋さんにお願いして、今日やっとこさ戻ってきました。
ウイルスだか何だかわかんないけど、帰ってきて何より。
データ失われてなくて何より。
壊されてなくて何より。。
ベトナムにしては結構高い値段とられてショックだけど、
パソコンに無知な俺にはしょうがない。
と、思いたいとこだけど・・・
たぶん原因はパソコンじゃなくて、アパートのインターネットケーブルにあったと思われる。
いや、絶対にケーブルだ!
修理のあんちゃんが修理したパソコン持ってきて繋いだら、
結局、修理前と接続状態あんまり変わらなくて、
あんちゃん困ったような顔してて、
微妙な沈黙つづいて、
挙句の果てに
「これはケーブルが悪いね。」
って言い出して、
大家さんにケーブル変えてもらったら、
つながった!!
って、、、
どういうこと!?
あんた「松野さんのパソコンはウイルスです・・・」
ってよくわからん片言の日本語で言うてたやん!!
ウイルスは???
いずこへ!?
まぁーそんなこんなもベトナムですな。
Take it easy!!
気楽にいきましょう。
さて、ネット世界から断絶されている間に、
日本では総選挙おわってました。
民主圧勝、自民大敗。
政治のことはよくわかりませんが、
日本よ、頼むから良くなってくれ!
国民は不安でなりません。
今はベトナム国民と化していますが。笑
日本に帰る頃までには政局が安定してるといいな。
ということで、海外においてパソコンがいかに重宝されるか、身に染みてわかった二週間でした。
敬具
追伸 小学校1年生の「国語の先生」始めました♪
まつのせんせいより