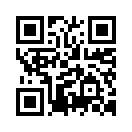2010年01月17日
同じきもち
先日、ベトナムでは希少な邦画DVDを、
ベトナム人の友だちに借りられたので、
今日見ました。
その映画は、

『硫黄島からの手紙』
数年前、「硫黄島」を日米両視点から捉えた二部作として話題になりましたよね。
個人的にはとても素晴らしい映画だと思いました。
私が観て育ったほとんどの戦争映画では、
どちらかが正義で、どちらかが悪だった。
しかし、人生とはそんなものではないし、戦争もそんなものではない。
この2本の映画は勝ち負けを描いたものではなく、
あの戦争が人間にどんな影響を与えたか、
そして戦争がなければもっと長く生きられたであろう人々のことを描いている。
と、イーストウッド監督が言うように、まさしく、戦争とは何か、
人間は何故戦うのか、を考えさせられる作品に仕上がってます。
しかし、ここで言う「人間は何故戦うのか」という観点は、
戦争が始まってからのそれぞれの人の想いであり、
やはり戦争自体が起こらない方向にもっていければ。
今なお世界では、内戦、紛争、テロ、、、
様々な形で、戦争が続いています。
決して過去の話ではありません。
いま、この瞬間も、です。
そして、日本では約60年前、
ここベトナムでは、つい30年前まで主戦場として戦争が繰り広げられていました。
今、僕が住んでいる“まさにこの場所”も戦場であったに違いありません。
恐ろしい数の罪のない人々が犠牲になる、そんな“日常”があったのです。
そう考えると、胸が締めつけられる想いに駆られます。。
戦争がよくないということは、誰もがみな、頭では分かっています。
でも、日々を生きるなかで
戦争を心の底から憎む気持ちをもつことはなかなかありません。
※主演:渡辺謙談
そうなんです、みんな戦争がよくないことは分かってるんです。
それでも起きてしまう現実。
どうしたものか・・・
しかし、戦場で行われていたことを見てしまったら、
自分の息子や恋人を決してそこに向かわせたくないと思うでしょう。
これこそ映画のもつ力ですよね。
映画を作るたびに制作費何億円とか桁外れな数字が並べられますが、
それでも、人々の心に訴えかける力があるから
それをも上回る興行収入を得られる。
お金の数の話は好きではありませんが、
でも、それだけの人が見て、何かしらを感じているということ。
大切にしたい文化です。
ただし、こんなにも影響力が強いからこそ、
気をつけなければならないのが、情報のバランス。
偏った情報は固定観念、ひいては偏見をもたらします。
作中にもこんなシーンがありました。
「アメリカ軍は腰抜けだ」「鬼畜米英」などと唱えていた日本兵小隊の中に
引きずり込まれた一人の若者米兵。
心優しき中佐の計らいで手当てを受けたが、まもなく息を引き取る。
そんな彼の胸から落ちた一片の手紙。
アメリカでの日常の生活が記された、母親からの愛情がつまった手紙だった。
そんなごく普通の生活を、みな自分の故郷や家族と重ねる。
「同じなんだ・・」
アメリカのきもち、日本のきもち、同じきもち---
固執したステレオタイプは「知らない」ことで生みだされるもの。
さらに、戦時下という境遇で無意識に刷り込まれていく情報。
インターネットが普及していないという時代背景があったものの、
情報統制とか外部情報の遮断って本当に怖い。
時は違えど、今起きている戦争においても同様のことが言える。
渦中にある兵士たちの思想は、偏った情報の刷り込みによって
意図的に「相手=悪」の認識を作り出されているのだろう。
片や、自分たちは絶対的に「正しい」。
そうとも思わなければ冷酷な戦場で戦い抜くことは出来ないのかもしれないが。
こうしたことも踏まえて「情報のバランス」という点で、
なおかつ微妙な政治的な問題をクリアし、
「人」という視点で作り出されている点で、
この作品は評価されるように思う。
『硫黄島からの手紙』ホームページ
アメリカから見つめた硫黄島『父親たちの星条旗』
日本に帰ったら観ようと思う。
最近、ふと考えることがある。
全世界が平和になること、それは可能なのだろうか・・。
できることなら成したい願い!
みなさんはどうお考えですか?
ベトナム人の友だちに借りられたので、
今日見ました。
その映画は、

『硫黄島からの手紙』
数年前、「硫黄島」を日米両視点から捉えた二部作として話題になりましたよね。
個人的にはとても素晴らしい映画だと思いました。
私が観て育ったほとんどの戦争映画では、
どちらかが正義で、どちらかが悪だった。
しかし、人生とはそんなものではないし、戦争もそんなものではない。
この2本の映画は勝ち負けを描いたものではなく、
あの戦争が人間にどんな影響を与えたか、
そして戦争がなければもっと長く生きられたであろう人々のことを描いている。
と、イーストウッド監督が言うように、まさしく、戦争とは何か、
人間は何故戦うのか、を考えさせられる作品に仕上がってます。
しかし、ここで言う「人間は何故戦うのか」という観点は、
戦争が始まってからのそれぞれの人の想いであり、
やはり戦争自体が起こらない方向にもっていければ。
今なお世界では、内戦、紛争、テロ、、、
様々な形で、戦争が続いています。
決して過去の話ではありません。
いま、この瞬間も、です。
そして、日本では約60年前、
ここベトナムでは、つい30年前まで主戦場として戦争が繰り広げられていました。
今、僕が住んでいる“まさにこの場所”も戦場であったに違いありません。
恐ろしい数の罪のない人々が犠牲になる、そんな“日常”があったのです。
そう考えると、胸が締めつけられる想いに駆られます。。
戦争がよくないということは、誰もがみな、頭では分かっています。
でも、日々を生きるなかで
戦争を心の底から憎む気持ちをもつことはなかなかありません。
※主演:渡辺謙談
そうなんです、みんな戦争がよくないことは分かってるんです。
それでも起きてしまう現実。
どうしたものか・・・
しかし、戦場で行われていたことを見てしまったら、
自分の息子や恋人を決してそこに向かわせたくないと思うでしょう。
これこそ映画のもつ力ですよね。
映画を作るたびに制作費何億円とか桁外れな数字が並べられますが、
それでも、人々の心に訴えかける力があるから
それをも上回る興行収入を得られる。
お金の数の話は好きではありませんが、
でも、それだけの人が見て、何かしらを感じているということ。
大切にしたい文化です。
ただし、こんなにも影響力が強いからこそ、
気をつけなければならないのが、情報のバランス。
偏った情報は固定観念、ひいては偏見をもたらします。
作中にもこんなシーンがありました。
「アメリカ軍は腰抜けだ」「鬼畜米英」などと唱えていた日本兵小隊の中に
引きずり込まれた一人の若者米兵。
心優しき中佐の計らいで手当てを受けたが、まもなく息を引き取る。
そんな彼の胸から落ちた一片の手紙。
アメリカでの日常の生活が記された、母親からの愛情がつまった手紙だった。
そんなごく普通の生活を、みな自分の故郷や家族と重ねる。
「同じなんだ・・」
アメリカのきもち、日本のきもち、同じきもち---
固執したステレオタイプは「知らない」ことで生みだされるもの。
さらに、戦時下という境遇で無意識に刷り込まれていく情報。
インターネットが普及していないという時代背景があったものの、
情報統制とか外部情報の遮断って本当に怖い。
時は違えど、今起きている戦争においても同様のことが言える。
渦中にある兵士たちの思想は、偏った情報の刷り込みによって
意図的に「相手=悪」の認識を作り出されているのだろう。
片や、自分たちは絶対的に「正しい」。
そうとも思わなければ冷酷な戦場で戦い抜くことは出来ないのかもしれないが。
こうしたことも踏まえて「情報のバランス」という点で、
なおかつ微妙な政治的な問題をクリアし、
「人」という視点で作り出されている点で、
この作品は評価されるように思う。
『硫黄島からの手紙』ホームページ
アメリカから見つめた硫黄島『父親たちの星条旗』
日本に帰ったら観ようと思う。
最近、ふと考えることがある。
全世界が平和になること、それは可能なのだろうか・・。
できることなら成したい願い!
みなさんはどうお考えですか?