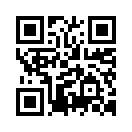2010年02月23日
ライフ
ベトナムの街が活き活きとしている理由が分かりました。
それは、仕事と生活の線引きがあいまいだから。
仕事の中に生活があったり、生活の中に仕事があったり。
まぁーよくも悪くも。
仕事しながら、ちゃっかり自分のご飯食べてたり、
接客しながら、携帯電話いじってたり、
DVD見たり、お笑い番組見て爆笑してたり、
店員同士ふざけあってたり、
客用のイス並べて昼寝してたり、、。
しかも、それらをお客の前で堂々と。
隠すそぶりなんてこれっぽっちもない(笑)

カンボジア行ってもやっぱりそうでした。
彼ら、彼女らには、きっと「サービス」なんて概念はないのでしょう。
でなきゃ、客よりも先にご飯は食べません。
「お客様=神様」なんて図式は頭の片隅にもないのでしょう。
でなきゃ、携帯片手にぶっきらぼうに接客しません。
つまり、客と店員は対等な立場なのです。


対して、日本はどうか。
素晴らしい。
非の打ちどころのない完璧なるサービス。
ゴミやら、食べかすやら、ライムやらが落ちてない綺麗な床。
不自然なまでの満面の笑みでの接客。
嫌な顔なんて一つもしません。
だって、
お客様は神様でございますから!
毎度ありがとうございます!
またのお越しをお待ちしております!
なんてベトナム人は絶対に言わないよ?笑
でも、俺が言いたいのはどちらが優れているというのではなくて、
そうした接客の態度や姿勢ひとつからでも
その国の国民性や文化、習慣、考え方、
つまり「その国らしさ」が見られるということ。
異国の日常に目を向けることは非常に面白い。
個人的には、東南アジアのゆるーい感じは嫌いじゃない。
むしろ、好きだ。
たまにイラッとはするけども、それもご愛嬌。
働くとしたら絶対に気楽だろうな。
仕事の現場から「苦」が感じられない。
いたって楽しんでいる。
それは生活の延長だから。
延長というか生活の中に包括されている。
「仕事」という気張った括りはないんだろうね、きっと。
だから、こっちの人の生活には活力があって、
活き活きとしてるんかなぁーなんて考えてみた。

そんな中での、心温まる「思いやり」だから、際立つ。
人の優しさがあったけーんだ。
日本のサービスにも感動するけど、
時にサービスの域を超えて“義務感”を感じることさえある。
もともとは思いやりから始まったサービスのはずなのに・・・。
矛盾だ。
こうした「しなければならない」サービスに従業員はストレスを覚えるのかもしれない。
先に、ベトナムでは仕事と生活の線引きがあいまいだと書いたが、
ある意味、日本でも、仕事と生活の境界が曖昧になっている。
常習化した残業。
残った仕事はお持ち帰り。
プライベートな時間をも仕事に費やし、
気づけばいつも仕事のことが頭から離れない。
「仕事」が「生活」の領域を脅かしている。
そういえば、こっちに来てから「自殺」って言葉聞いてないな。
この国も日本と同じ軌跡を辿るのだろうか。
「発展」とはなんぞや!?と、考える今日この頃。
チャーオ。

何だよ、そのポージング(笑)
おまえ、可愛すぎるよ。
※「仕事も生活だ」という意見もあると思いますが、ここでは限定的に「生活」を定義しています。
それは、仕事と生活の線引きがあいまいだから。
仕事の中に生活があったり、生活の中に仕事があったり。
まぁーよくも悪くも。
仕事しながら、ちゃっかり自分のご飯食べてたり、
接客しながら、携帯電話いじってたり、
DVD見たり、お笑い番組見て爆笑してたり、
店員同士ふざけあってたり、
客用のイス並べて昼寝してたり、、。
しかも、それらをお客の前で堂々と。
隠すそぶりなんてこれっぽっちもない(笑)
カンボジア行ってもやっぱりそうでした。
彼ら、彼女らには、きっと「サービス」なんて概念はないのでしょう。
でなきゃ、客よりも先にご飯は食べません。
「お客様=神様」なんて図式は頭の片隅にもないのでしょう。
でなきゃ、携帯片手にぶっきらぼうに接客しません。
つまり、客と店員は対等な立場なのです。
対して、日本はどうか。
素晴らしい。
非の打ちどころのない完璧なるサービス。
ゴミやら、食べかすやら、ライムやらが落ちてない綺麗な床。
不自然なまでの満面の笑みでの接客。
嫌な顔なんて一つもしません。
だって、
お客様は神様でございますから!
毎度ありがとうございます!
またのお越しをお待ちしております!
なんてベトナム人は絶対に言わないよ?笑
でも、俺が言いたいのはどちらが優れているというのではなくて、
そうした接客の態度や姿勢ひとつからでも
その国の国民性や文化、習慣、考え方、
つまり「その国らしさ」が見られるということ。
異国の日常に目を向けることは非常に面白い。
個人的には、東南アジアのゆるーい感じは嫌いじゃない。
むしろ、好きだ。
たまにイラッとはするけども、それもご愛嬌。
働くとしたら絶対に気楽だろうな。
仕事の現場から「苦」が感じられない。
いたって楽しんでいる。
それは生活の延長だから。
延長というか生活の中に包括されている。
「仕事」という気張った括りはないんだろうね、きっと。
だから、こっちの人の生活には活力があって、
活き活きとしてるんかなぁーなんて考えてみた。
そんな中での、心温まる「思いやり」だから、際立つ。
人の優しさがあったけーんだ。
日本のサービスにも感動するけど、
時にサービスの域を超えて“義務感”を感じることさえある。
もともとは思いやりから始まったサービスのはずなのに・・・。
矛盾だ。
こうした「しなければならない」サービスに従業員はストレスを覚えるのかもしれない。
先に、ベトナムでは仕事と生活の線引きがあいまいだと書いたが、
ある意味、日本でも、仕事と生活の境界が曖昧になっている。
常習化した残業。
残った仕事はお持ち帰り。
プライベートな時間をも仕事に費やし、
気づけばいつも仕事のことが頭から離れない。
「仕事」が「生活」の領域を脅かしている。
そういえば、こっちに来てから「自殺」って言葉聞いてないな。
この国も日本と同じ軌跡を辿るのだろうか。
「発展」とはなんぞや!?と、考える今日この頃。
チャーオ。
何だよ、そのポージング(笑)
おまえ、可愛すぎるよ。
※「仕事も生活だ」という意見もあると思いますが、ここでは限定的に「生活」を定義しています。