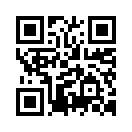2009年12月01日
大運動会
今日は12月1日。
何の日か知ってますか?
“世界エイズデー”
小さなことでいいから世界に貢献する自分でありたい。
ベトナムに来てから、そう思える自分に一歩近づきました。
前にもおすすめしましたが、“エイズデー”にちなんで一曲紹介。
RED RIBBON Spiritual Song ~生まれ来る子供たちのために~
すごくいい曲なんで、一度聞いてみてください。
小田和正さんの不朽の名作がAIDS チャリティ Project によってリメークされたものです。
今年話題の絢香さんも歌ってますよ!
そして、最近見つけたいい言葉・・・
「有り余るほどに恵まれた環境で与えられたものを持て余している」
そう感じたときに気がついたのは、
「持たない者を補うために1人分よりも多く持たされている」
ということだった。
誰しもが渇望して生きること、
それ自体を諦めざるを得ない人に私が持たされた“それ”を届けたい。
「ベトナムの赤ひげ」こと眼科医・服部先生(この人もすごい!!)の
お手伝いとしてボランティア活動を体験した医学生の言葉です。〔ビナBOOより〕
恵まれた世界に生きているとき、そのことに気づくことは結構難しい。
前置きがだいぶ長くなりました(汗)
さて、タイトルの「大運動会」は、
先日、“先生”として初めて参加した運動会のことです。
その名も、「ホーチミン日本人学校大運動会」!!
そのままですね。

ただ、僕たちの参加は日本人学校としてではなく、
ホーチミン日本人補習校として。
状況から言って「参加させてもらった」という方が正しいのかもしれません。
正直、肩身は狭かったです。
その立場ゆえ難しいことが多々ありました。
また、久しぶりに運動会というものに参加してみて感じたことが色々とありました。
まず、補習校としての参加が何を意味するかというと、
練習なし、“ぶっつけ本番”で臨むということ。
すなわち、運動会なるものを全く知らない子ども達が、
そこまでするか!というほどに練習してきた子ども達と共にするということです。
皆さんも自分が小学生だったころを思い出してみてください。
我が子がいる方は、お子さんの運動会を思い浮かべてみてください。
理路整然とした入場行進。
練り上げられた選手宣誓。
体育係によるラジオ体操。
メイン以上に繰り返される入退場練習。
それぞれ学校によって特色はあると思いますが、
日本人が思い浮かべる「運動会」はみな似たものではないでしょうか。
練習に練習を重ねた学校の一大イベントであったはずです。
では、外国人が「運動会」を思い浮かべるとどうなるか・・・
正解は、
「思い浮かばない」
です。
運動会って日本だけの独特な行事なんですよ。
全世界で行われているものだと思っていませんでしたか?
案外、知らない日本人も多いと思います。
よって、日本の教育を受けてこなかった補習校の生徒たちが、
運動会に参加するとどうなるか・・・
セパレートコースがセパレートでない。
=「斜め横断」走。
スタートのタイミングがわからない。
フライングの嵐。
もはや止められない。
リードってなんだ?
バトンパスする相手を追い越す。
そもそも、リレーって何だよ。
行進って気持ち悪いね。
なんであんなに揃ってんの?
まるで軍隊みたい・・・。
ってなことになります。
幸い、同じ学年の先生の提案で、前日に少し練習しておいたので、
うちの学年は一年生ながら、それなりに頑張っていましたが、
全く知らない生徒たちはもはや無法地帯。
おかげ様で、子どもに紛れて、
来賓の皆様、保護者の皆様、校長先生をはじめ諸先生方の目の前を“堂々と”行進しました。
ウソです。
“細々と”行進しました。。
当たり前だと思っていることって本当に「当たり前」じゃない。
当然のごとく運動会を経験してきた僕たちにとって、
彼らの思うことや行動が新鮮でした。
特にラジオ体操は顕著でした。
日本でやったことがある生徒ならまだしも、
やったことがない生徒は本当に全然できない。
見よう見まねでもできない。
冷静に考えたらラジオ体操って奇怪な動きが多いしね(笑)
そんな子ども達を見ていて、微笑ましく思ってしまった松野先生は、
手本を示そうと彼らの横で誰よりもラジオ体操を頑張りました。
彼らのぎこちない動きを見ながら、表情もさぞにやけていた事でしょう。
その結果、のちに、ある保護者の方から
「ラジオ体操、松野先生が一番楽しんでましたねー」
と言われてしまったのは想像に難くありません。
間違いないです。
僕が一番楽しんでました。
もう一つ顕著だったのは、開・閉会式の生徒たちの様子。
全員が直立不動で式辞を見聞きする日本人学校の生徒に対して、
目のやり場に困る補習校生徒。
どうやら落ち着いてられないご様子。
・・・そりゃそうだ。
インターナショナルスクールでそんな格式ばった式なんてないもの。
授業ですら、出歩く生徒がいて然りというんですから。
そんな様子を見ていて、自由な感じでいいんじゃないかなー
なーんて、校風の違いを楽しんでいた不謹慎な先生は私です。
こうした式なんかもそうだし、ラジオ体操や応援合戦など、
また、運動会というイベント自体が広く親しまれるようになったのは、
やはり戦争をしていた時代の影響だと思う。
富国強兵を掲げる日本軍が兵式体操としてラジオ体操を取り入れたのは、
有名な話ですよね。
一つひとつの場がみんなで同じ行動をするという統制された場となり、
体には自然と「正しい」行動や規律が叩き込まれる。
気づかないけど無意識にそういう行動様式に取り込まれていることって
日本の日常生活、特に学校生活の中で数多くある気がする。
今なお、そうした名残が色濃くあるように思う。
勤勉なところや「和」を重んじる日本人の気質も
そんなとこから来てるんじゃないかなぁーと考えてみた。
「運動会の社会学」って大学院のゼミで勉強した気がするけど、、、
忘れちゃった。
先生、すみません。。
出直してきます!
でもね、なんだかんだいって、
当の子どもたちは始まってしまえば、みーんな楽しそうにやるから素敵。
正直、補習校の生徒にとっては肩身の狭いイベントだし、
AWAYな感も否めないし、出場種目も少ないし、
ましてや練習なんてしてないからリレーなんて大差で負けちゃうし・・・。
(リレー担当に任された新米2人は、深く反省しているのです。)
でも、生徒たちはみんな一生懸命で、本当に楽しそうにしてる。
大概、不平や不満を言うのは大人であって、
わたしたちはそうした子どもたちのピュアな心を見習い
彼ら一人ひとりの心に添って、全力でサポートすべきではないか。
「ディフェンスが下手だからファールして止めるしかないんだ。」
Kが言ってたそんな比喩(明神の言葉だっけ?)がしみじみと思い浮かばれます。
たとえそこに不公平が生まれたとしても、子どもたちに罪はない。
全てを平等にすることは不可能かもしれないけど、
それをイーブンに近づける努力は常にしていたい。
恵まれた環境にいるときこそ、なおさらだ。
何の日か知ってますか?
“世界エイズデー”
小さなことでいいから世界に貢献する自分でありたい。
ベトナムに来てから、そう思える自分に一歩近づきました。
前にもおすすめしましたが、“エイズデー”にちなんで一曲紹介。
RED RIBBON Spiritual Song ~生まれ来る子供たちのために~
すごくいい曲なんで、一度聞いてみてください。
小田和正さんの不朽の名作がAIDS チャリティ Project によってリメークされたものです。
今年話題の絢香さんも歌ってますよ!
そして、最近見つけたいい言葉・・・
「有り余るほどに恵まれた環境で与えられたものを持て余している」
そう感じたときに気がついたのは、
「持たない者を補うために1人分よりも多く持たされている」
ということだった。
誰しもが渇望して生きること、
それ自体を諦めざるを得ない人に私が持たされた“それ”を届けたい。
「ベトナムの赤ひげ」こと眼科医・服部先生(この人もすごい!!)の
お手伝いとしてボランティア活動を体験した医学生の言葉です。〔ビナBOOより〕
恵まれた世界に生きているとき、そのことに気づくことは結構難しい。
前置きがだいぶ長くなりました(汗)
さて、タイトルの「大運動会」は、
先日、“先生”として初めて参加した運動会のことです。
その名も、「ホーチミン日本人学校大運動会」!!
そのままですね。
ただ、僕たちの参加は日本人学校としてではなく、
ホーチミン日本人補習校として。
状況から言って「参加させてもらった」という方が正しいのかもしれません。
正直、肩身は狭かったです。
その立場ゆえ難しいことが多々ありました。
また、久しぶりに運動会というものに参加してみて感じたことが色々とありました。
まず、補習校としての参加が何を意味するかというと、
練習なし、“ぶっつけ本番”で臨むということ。
すなわち、運動会なるものを全く知らない子ども達が、
そこまでするか!というほどに練習してきた子ども達と共にするということです。
皆さんも自分が小学生だったころを思い出してみてください。
我が子がいる方は、お子さんの運動会を思い浮かべてみてください。
理路整然とした入場行進。
練り上げられた選手宣誓。
体育係によるラジオ体操。
メイン以上に繰り返される入退場練習。
それぞれ学校によって特色はあると思いますが、
日本人が思い浮かべる「運動会」はみな似たものではないでしょうか。
練習に練習を重ねた学校の一大イベントであったはずです。
では、外国人が「運動会」を思い浮かべるとどうなるか・・・
正解は、
「思い浮かばない」
です。
運動会って日本だけの独特な行事なんですよ。
全世界で行われているものだと思っていませんでしたか?
案外、知らない日本人も多いと思います。
よって、日本の教育を受けてこなかった補習校の生徒たちが、
運動会に参加するとどうなるか・・・
セパレートコースがセパレートでない。
=「斜め横断」走。
スタートのタイミングがわからない。
フライングの嵐。
もはや止められない。
リードってなんだ?
バトンパスする相手を追い越す。
そもそも、リレーって何だよ。
行進って気持ち悪いね。
なんであんなに揃ってんの?
まるで軍隊みたい・・・。
ってなことになります。
幸い、同じ学年の先生の提案で、前日に少し練習しておいたので、
うちの学年は一年生ながら、それなりに頑張っていましたが、
全く知らない生徒たちはもはや無法地帯。
おかげ様で、子どもに紛れて、
来賓の皆様、保護者の皆様、校長先生をはじめ諸先生方の目の前を“堂々と”行進しました。
ウソです。
“細々と”行進しました。。
当たり前だと思っていることって本当に「当たり前」じゃない。
当然のごとく運動会を経験してきた僕たちにとって、
彼らの思うことや行動が新鮮でした。
特にラジオ体操は顕著でした。
日本でやったことがある生徒ならまだしも、
やったことがない生徒は本当に全然できない。
見よう見まねでもできない。
冷静に考えたらラジオ体操って奇怪な動きが多いしね(笑)
そんな子ども達を見ていて、微笑ましく思ってしまった松野先生は、
手本を示そうと彼らの横で誰よりもラジオ体操を頑張りました。
彼らのぎこちない動きを見ながら、表情もさぞにやけていた事でしょう。
その結果、のちに、ある保護者の方から
「ラジオ体操、松野先生が一番楽しんでましたねー」
と言われてしまったのは想像に難くありません。
間違いないです。
僕が一番楽しんでました。
もう一つ顕著だったのは、開・閉会式の生徒たちの様子。
全員が直立不動で式辞を見聞きする日本人学校の生徒に対して、
目のやり場に困る補習校生徒。
どうやら落ち着いてられないご様子。
・・・そりゃそうだ。
インターナショナルスクールでそんな格式ばった式なんてないもの。
授業ですら、出歩く生徒がいて然りというんですから。
そんな様子を見ていて、自由な感じでいいんじゃないかなー
なーんて、校風の違いを楽しんでいた不謹慎な先生は私です。
こうした式なんかもそうだし、ラジオ体操や応援合戦など、
また、運動会というイベント自体が広く親しまれるようになったのは、
やはり戦争をしていた時代の影響だと思う。
富国強兵を掲げる日本軍が兵式体操としてラジオ体操を取り入れたのは、
有名な話ですよね。
一つひとつの場がみんなで同じ行動をするという統制された場となり、
体には自然と「正しい」行動や規律が叩き込まれる。
気づかないけど無意識にそういう行動様式に取り込まれていることって
日本の日常生活、特に学校生活の中で数多くある気がする。
今なお、そうした名残が色濃くあるように思う。
勤勉なところや「和」を重んじる日本人の気質も
そんなとこから来てるんじゃないかなぁーと考えてみた。
「運動会の社会学」って大学院のゼミで勉強した気がするけど、、、
忘れちゃった。
先生、すみません。。
出直してきます!
でもね、なんだかんだいって、
当の子どもたちは始まってしまえば、みーんな楽しそうにやるから素敵。
正直、補習校の生徒にとっては肩身の狭いイベントだし、
AWAYな感も否めないし、出場種目も少ないし、
ましてや練習なんてしてないからリレーなんて大差で負けちゃうし・・・。
(リレー担当に任された新米2人は、深く反省しているのです。)
でも、生徒たちはみんな一生懸命で、本当に楽しそうにしてる。
大概、不平や不満を言うのは大人であって、
わたしたちはそうした子どもたちのピュアな心を見習い
彼ら一人ひとりの心に添って、全力でサポートすべきではないか。
「ディフェンスが下手だからファールして止めるしかないんだ。」
Kが言ってたそんな比喩(明神の言葉だっけ?)がしみじみと思い浮かばれます。
たとえそこに不公平が生まれたとしても、子どもたちに罪はない。
全てを平等にすることは不可能かもしれないけど、
それをイーブンに近づける努力は常にしていたい。
恵まれた環境にいるときこそ、なおさらだ。